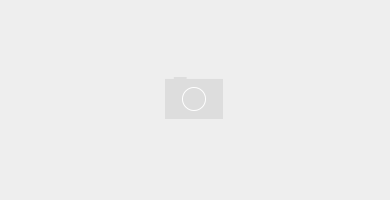血糖値スパイクとは?
血液の中の糖質の割合を血糖値と言いますが、これをコントロールすることはとても大事です。
血糖値が正常でないと、体にいろいろな悪影響を及ぼすからです。
その一つの問題として、血糖値スパイクと呼ばれる現象に注目が集まっています。
この血糖値スパイクとは、食事をした後に急激に血糖値が上がるという現象です。
血糖値は当然食事によって変わってきますので、食事をすれば糖質が血液中に入っていき血糖値が上昇するのは普通です。
しかし、その上昇が通常ではない場合に血糖値スパイクとなるのです。
血糖値スパイクが起きている人は、その変化を一種の自覚症状として感じることが多いです。
たとえば、食後に強い疲労感や倦怠感を覚えて、椅子やソファーでぐったりとしていることが多いといったものです。
また、眠気が強くなって眠らないと昼食後の活動ができないといったケースも当てはまります。
このように、全体として食後に元気がなくなり、体を動かすのが難しい場合血糖値スパイクが疑われるわけです。
血糖値スパイクにはどんなリスクがある?
こうした自覚症状を見せる血糖値スパイクは、血糖値が食後2時間程度の時点で140mg/dオーバーとなっていると起こります。
この数値がずっと落ちずに続くようだと、糖尿病と診断されることになります。
しかし血糖値スパイクの場合、食前や食後数時間経つと血糖値が下がり、正常な状態に戻ります。
食後の1、2時間のみとても高い血糖値を示すのが血糖値スパイクの特徴と言えます。
こうした血糖値の大きな上下は、血管にダメージを与えます。
血管がもろくなるとか硬化しやすくなるという影響があり、それが続くと動脈硬化や本格的な糖尿病の合併症と同じ問題を引き起こすことになります。
さらに血管関連の深刻な症状を引き起こし、脳卒中や心筋梗塞などのリスクを高めることもあります。
こうしたことから、糖尿病患者ではないとしても、血糖値スパイクの傾向が見られるのであれば早めにきちんとした対処をする必要があるのです。
糖質ばかりの食事は避けることが重要
食後に血糖値が上がり、その他の時間は正常であることから血糖値スパイクは見過ごされがちです。
しかし、健康リスクは高いので、食事を気を付けるなどの対策をすべきです。
具体的には、糖質が多い食事は避けるべきです。
たとえば朝食ではパンやコーンフレークなどの炭水化物ばかりで、野菜やヨーグルトなどのたんぱく質を摂っていないと、血糖値スパイクが起こりやすいことが分かっています。
そのため、炭水化物は重要ですが、同時に食物繊維やタンパク質を意識して一緒に摂ることが重要です。
また、食べる順番もいきなりご飯やパンなどの糖質ではなく、初めに野菜やタンパク質を摂るようにすると糖の吸収が緩やかになってリスクを減らせることも分かっています。